豆知識
2025/10/01
溶融亜鉛めっきを左右する鋼材の化学成分とは?影響や管理方法を解説
おすすめ記事
- RANKING
- 最近人気の記事
- SDS(安全データシート)とは?見方をわかりやすく解説
- 溶融亜鉛めっき上の塗装はできる?耐食性と美観を両立させたい方は必見!
- 溶融亜鉛めっきの白さびは悪者?原因と対策、新たな視点を解説
- 溶融亜鉛めっきのJIS規格の改正について
- 専用シンナー(うすめ液)以外はNG!理由や不具合の事例を解説
- 溶融亜鉛めっきと異種金属が接触したら腐食する?メカニズムを解説
- 無機ジンクと有機ジンクは何が違う?1液と2液の違いも解説
- ジンクリッチペイントとは?亜鉛含有率との関係や防錆メカニズムを解説
- 溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
- 溶融亜鉛めっきと塗装は何が違う?両者の特徴をわかりやすく比較
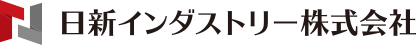
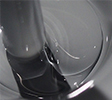





「めっきの付き方にバラつきがあるが、原因がわからない...。」とお困りではありませんか?
もしかすると鋼材の化学成分が影響しているのかもしれません。
本記事では、溶融亜鉛めっきを左右する化学成分について、掘り下げて解説しています。
不具合事例や品質管理の方法にも触れていますので、めっきの不具合にお困りの方は、ぜひ最後までお読みください。
なぜ鋼材の化学成分が溶融亜鉛めっきに影響するのか
溶融亜鉛めっきは、鉄と亜鉛が反応して合金層が形成されることで成り立つ表面処理です。
鋼材に含まれる化学成分によって、鉄と亜鉛の反応の進み方が変わります。
シリコンやリンが多いと反応が速くなりすぎてめっき層が厚くなる場合もあります。
また鋼材の成分は、表面にできる酸化被膜や結晶組織の状態にも影響を与える要因です。
例えば、酸化アルミニウムが表面に残っていれば亜鉛が付着しにくくなり、炭素量が多ければ組織が不均一になって反応にムラが出ます。
このように、化学成分は鉄と亜鉛の反応条件を左右するため、めっき層の成長速度、膜の厚み、密着性、外観、耐食性といった品質に直結するのです。
溶融亜鉛めっきに影響を与える鋼材の化学成分
一般的な鋼材には以下の成分が含まれており、それぞれ溶融亜鉛めっきに影響を与える可能性があります。
それぞれについて、掘り下げて確認していきましょう。
シリコン(Si)
シリコン(Si)は、鋼材の精錬時に添加される化学成分であり、鋼中の酸素と結合させるための脱酸材として使用されます。
鋼に酸素が残ると、気泡が内部欠陥になってしまうため、シリコンは重要な存在です。
鋼材に含まれるシリコンの量が0.02%以下もしくは0.15%以上の場合は、鉄と亜鉛の反応速度は安定していますが、0.03~0.12%の時は反応速度が速くなります。
反応速度が速くなることで、時短で作業性が向上する場合もありますが、安定時と比較して1.5~2倍程度の膜厚化が起こり、密着性低下や「やけ」と呼ばれる外観不良が起こる可能性が高まります。
シリコンは溶融亜鉛めっきの品質において、最も重要な化学成分です。
リン(P)
リン(P)は、鋼材に不純物として含まれる化学成分です。
鋼の強度を上げる一方で、多量になると鋼を脆くして、割れやすくします。
リンは単独でも他の成分と複合してもめっき反応に大きな影響を与える化学成分です。
リンの含有量が増加すると合金反応が活発になりますが、活発になりすぎるとめっき層が剥離する可能性が高まります。
シリコンとの複合作用については、以下が異常反応の判定基準です。
【シリコン(Si) + 2.5 × リン(P) > 0.09%】
この計算式に当てはめた時に、0.09%以下の場合は、安定しためっき付着となります。
逆に0.09%を超える場合は過剰な付着が懸念されるため、注意が必要です。
例えば、鋼材中のシリコンとリンが共に0.02%であれば、0.02+(2.5×0.02)=0.07%となり、めっきが安定付着する鋼材だといえます。
マンガン(Mn)
マンガン(Mn)は、鋼材に含まれる酸素や硫黄と結合させる脱酸・脱硫剤として使用される化学成分です。
また添加することによって、鋼材の強度が上がります。
鋼材に含まれるマンガンの割合が1.2%を超えると、反応促進効果が現れて、亜鉛の付着量が増大します。
過剰なマンガンの添加は、やけや密着性の低下などの原因です。
炭素(C)
鋼材における炭素(C)は、含有量によって硬さや強度を調整する役割を担っています。
炭素量が多いほど硬い鋼材になるのが特徴です。
鋼材に含まれる炭素の割合が0.08%以下の低炭素鋼は均一な反応特性を示します。
一方で0.08~0.15%の中炭素鋼や0.15%以上の高炭素鋼では、組織の不均一による反応ムラが起きやすくなり、局所的にめっき層が厚かったり、薄かったりと外観に影響が出ることもあります。
アルミニウム(Al)
アルミニウムは、シリコンと同じく鋼材の脱酸剤として使用される化学成分です。
また微量のアルミニウムは、鋼の粘り強さを高める働きがあります。
鋼材に含まれるアルミニウムの割合が0.03以下の場合は、亜鉛との反応は安定していますが、0.05%以上になると、合金層の成長が抑制されるようになり、めっきが薄くなる原因となります。
鋼材の化学成分による不具合事例と解決策
画像:溶融亜鉛めっきのやけ事例
前述した鋼材に含まれる化学成分によって起こる、溶融亜鉛めっきの不具合事例には以下があります。
それぞれの詳細と解決策を確認していきましょう。
シリコンとリンによる膜厚・灰色化
鋼材に含まれるシリコンとリンは、溶融亜鉛めっきの反応を大きく左右する化学成分です。
前述した計算式に当てはめてみて、異常反応の判定基準を上回っていると、鉄と亜鉛の反応は異常に進みやすくなります。
この時に溶融亜鉛めっきに起こるのが、皮膜の膜厚化と表面が灰色を帯びて「やけ」と呼ばれる灰色化です。
外観不良になるのはもちろんですが、合金層が粗大化することによって、鋼材との密着性が下がり、部分的な剥離や耐食性のバラつきにもつながる不具合となります。
アルミニウム酸化被膜の残存によるめっき不着
アルミニウムを多く含む鋼材では、表面にアルミニウムの強固な酸化被膜が自然に形成されます。
この酸化被膜は非常に強力で酸洗処理やフラックス処理でも完全に除去しにくいのが特徴です。
仮にアルミニウム酸化被膜が残存した状態で、溶融亜鉛めっき浴に鋼材を漬けた場合、亜鉛が反応できない部分が生じて、めっきが付かない不着不良が起こります。
めっきの不着部は鋼材がむき出しの状態なので、防錆性能が乏しく、使用時にサビが侵食するリスクが高まるため、注意が必要です。
めっき不具合を防ぐ鋼材の化学成分の品質管理
鋼材のめっき不具合を防ぐためには、鋼材に含まれる化学成分の品質管理が欠かせません。
品質管理のポイントは以下のとおりです。
それぞれの詳細を確認していきましょう。
総合的な管理が大切
めっき不良の原因は、本記事でピックアップした鋼材に含まれる化学成分だけではありません。
表面処理の方法やめっき浴の温度、浸漬時間、冷却方法など、いくつもの条件が重なって不具合は発生します。
例えば、シリコンやリンが多い鋼材では、めっき浴の浸漬時間を変えなければ、反応が進みすぎてしまい、灰色化の不具合につながります。
この場合は、めっき浴の温度調整や浸漬時間の短縮が有効です。
めっき不具合を予防するために鋼材の化学成分に注目することは大切ですが、それだけではなく工程全体を見直してバランス良く管理することが、めっきを安定させるためには欠かせません。
高精度分析技術の活用
最近は分析の精度が大きく向上しており、鋼材にどんな成分がどのくらい入っているかを細かく調べられるようになっています。
例えば、蛍光X線分析(XRF)と呼ばれるX線を使った装置では、ラインを流れる鋼材をその場でチェックでき、問題がありそうなロットをすぐに判別可能です。
さらに、誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)などの高性能な分析装置を使えば、0.001%レベルのわずかな成分まで見つけることができ、不具合の原因を事前に察知できます
こうした高精度の分析技術を活用することで、データを根拠にした予防的な管理が可能です。
AI・IoTシステムの活用
工場でもデジタル化が進み、AIやIoTを活用した管理が増加中です。
めっきラインでは、鋼材の成分や浴の温度・時間などのデータをセンサーで常時収集し、それをAIが解析します。
例えば、シリコンが多く含まれる鋼材が流れてきたら、自動で浸ける時間を短くするといった調整も可能です。
経験豊富な作業者の「勘」に頼らなくても、データに基づいた安定した生産が可能となります。
まとめ:溶融亜鉛めっきの安定生産には化学成分の管理が重要
溶融亜鉛めっきの品質には、鋼材の化学成分が大きく影響しています。
安定した生産を行うためには、鋼材に含まれる化学成分を把握・管理することが重要です。
近年では溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウムの高耐食性の合金めっきが広く使用されています。
日新インダストリーでは、従来の溶融亜鉛めっきの補修用ジンク塗料に加えて、高耐食性めっきにも対応できる補修剤『マザックス』と環境対応型の『マザックスネオ』を取り扱っております。
気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
■商品ページ:『マザックス』
■商品ページ:『マザックスネオ』