豆知識
2025/10/31
溶融亜鉛めっき高力ボルトとは?接合時のポイントや注意点を解説
おすすめ記事
- RANKING
- 最近人気の記事
- SDS(安全データシート)とは?見方をわかりやすく解説
- 溶融亜鉛めっき上の塗装はできる?耐食性と美観を両立させたい方は必見!
- 溶融亜鉛めっきの白さびは悪者?原因と対策、新たな視点を解説
- 溶融亜鉛めっきのJIS規格の改正について
- 専用シンナー(うすめ液)以外はNG!理由や不具合の事例を解説
- 溶融亜鉛めっきと異種金属が接触したら腐食する?メカニズムを解説
- 無機ジンクと有機ジンクは何が違う?1液と2液の違いも解説
- ジンクリッチペイントとは?亜鉛含有率との関係や防錆メカニズムを解説
- 溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
- 溶融亜鉛めっきと塗装は何が違う?両者の特徴をわかりやすく比較
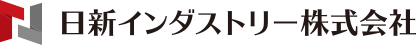
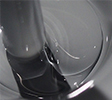





「溶融亜鉛めっき高力ボルトを使うように指示があったけれど、一般の高力ボルトと何が違うの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
溶融亜鉛めっき高力ボルトは、一般的な高力ボルトと違ってJIS規格品がなく、施工時にも様々なポイントがあります。
本記事では、溶融亜鉛めっき高力ボルトの接合についてわかりやすく解説しています。
溶融亜鉛めっき高力ボルトを使って接合を行いたいと考えている人は必見です。
溶融亜鉛めっき構造物の接合法
溶融亜鉛めっき構造物を接合する際は、大きく分けて以下2つのアプローチがあります。
それぞれを詳しく確認していきましょう。
部分的なめっき施工
画像:不めっき処理をした鉄骨
橋梁などの大型構造物では高力ボルトによる摩擦接合が多用されています。
溶融亜鉛めっき処理をした鋼材の表面はツルツルしてすべりやすく、接合面のすべり係数を確保できません。
そのため、接合面にはめっき処理を行わず、その他を部分的にめっき施工する方法が一般的です。
亜鉛槽にドブ漬けする溶融亜鉛めっきの場合は、接合面にめっきが付かないように「不めっき処理」を行います。
高力ボルトを接合した後に、ジンク塗料で防錆処理を行うのが一般的です。
不めっき処理については、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。
参考:溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
全面めっき施工
ボルト、ナット、座金を含めて全てにめっき処理を施したものを使うのが、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合です。
一般的な高力ボルトは、ジンク塗料による定期的なメンテナンスが欠かせませんが、溶融亜鉛めっき高力ボルトを使えば、真のメンテナンスフリー構造を実現できます。
溶融亜鉛めっき高力ボルトは、長期的な耐食性に優れているので、海岸地域など腐食環境の厳しい場所やメンテナンスが困難な現場では有効的です。
溶融亜鉛めっき高力ボルトとは?
溶融亜鉛めっき高力ボルトの特徴は以下のとおりです。
それぞれの特徴を掘り下げて確認していきましょう。
JIS規格品ではなく国土交通大臣の認定が必要
溶融亜鉛めっき高力ボルトは、摩擦接合用高力ボルトの規格であるJIS B 1186には含まれておらず、国土交通大臣の認定を受けた専用製品として扱われます。
これは通常のJIS規格品である高力ボルトと異なり、溶融亜鉛めっきによるねじ部の寸法変化や摩擦係数の低下など、接合性能に影響する可能性があるためです。
溶融亜鉛めっき高力ボルトの認定品では、めっき後のねじ精度や締め付け特性、摩擦係数などの実験で検証を行い、安全に使用できるかどうかが必ず確認されています。
認定されているのはF8Tのみ
画像:溶融亜鉛めっき高力ボルトF8Tを使用した施工
一般的な高力ボルトの強度グレードはF10Tですが、溶融亜鉛めっき高力ボルトの強度グレードはF8Tのみが認定されています。
強度だけで見ると、一般的な高力ボルトの方が強いですが、なぜでしょうか。
これにはボルトをドブ漬けする亜鉛槽の温度が関係しています。
溶融亜鉛めっきは、約420℃以上に溶融した亜鉛槽に製品を漬けますが、この温度がF10Tの焼き戻し温度を上回っているのです。
焼き戻しは、焼入れで硬くなった素材の粘り強さを高める工程ですが、その代償として強度が低下します。
F8Tの焼き戻し温度は約500℃以上のため、溶融亜鉛めっき処理を行っても強度の低下がありません。
そのため、F8Tのみが認定されています。
厳格なめっき品質基準がある
溶融亜鉛めっき高力ボルトでは、適切な接合性能を確保するために、以下のとおりめっき品質が厳格に定められています。
めっきが厚いまたは不均一な場合、摩擦係数が不安定になり、適切な摩擦接合に影響を及ぼしかねません。
そのため、上記のとおり厳しい品質基準が定められています。
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工時のポイント
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工時のポイントには以下があります。
その他のポイントも含めて、確認していきましょう。
適切な下地処理を行う
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合においては、摩擦接合性能(すべり係数μ=0.40)を確保するために以下の下地処理が必須です。
溶融亜鉛めっき高力ボルトの接合面は、ショットブラストまたはサンドブラストを施し、めっき表面の光沢層や酸化被膜を除去します。
つまりツルツルした面を取り除き、接合面に凹凸を形成させる処理です。
この処理を行うことで、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合時に、ボルト軸力による面圧と嚙合わせ効果が高まり、すべり係数を0.40程度まで向上させます。
ナット回転法で締め付ける
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のナット回転法では、1次締め(仮締め)と本締めの2段階で締め付けます。
まず1次締めでは、全てのボルトを均等に締め付け、接合部の摩擦面を完全に密着させます。
目的は、部材の浮きや隙間をなくすことです。1次締め後には、ボルト・ナット・座金の位置をマーキングし、本締め時の回転角度を確認できるようにします。
次に本締めでは、規定された角度(例:120°や180°など)ナットを回転させて、所定の軸力を正確に導入します。
トルク値に依存しないため、摩擦係数の変動が大きい溶融亜鉛めっきボルトでも、安定した軸力とすべり係数を確保できるのがナット回転法の特徴です。
ボルト、ナット、座金は同一セット品を使用する
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合を行う際は、ボルト、ナット、座金は必ず同一セット品を使用しなければなりません。
これは設計通りの軸力と摩擦性能を確実に発揮させるためです。
異なるメーカーや規格品を混用すると、ねじのかみ合わせ精度や座金の変形特性が揃わず、軸力がばらつく恐れがあります。
その他のポイント
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工時の、その他ポイントは以下の通りです。
このように使用するにあたっては、適切な技術的配慮が必要となります。
取り扱い時の注意点も含めて、理解を深めた上で使用するようにしましょう。
溶融亜鉛めっき高力ボルトのメリットと注意すべき課題
・後からの防錆処理が不要
・ナット回転法による締め付けが可能で、トルク管理が難しい現場でも施工できる
・認定技術者による施工管理が必要
・リラクセーションが起こりやすい
上記は溶融亜鉛めっき高力ボルト接合のメリットと注意すべき課題をまとめた表です。
優れた防錆性能によるメンテナンスフリーを実現できるのが最大のメリットだといえます。
一般的な高力ボルトの場合、施工後にジンク塗料で防錆処理を行う必要がありますが、溶融亜鉛めっき高力ボルトでは後からの防錆処理は不要です。
一方で施工時には、認定技術者による施工管理が必要であり、高力ボルトよりも2~3倍の張力減少(リラクセーション)が起こるのが注意すべき課題となります。
まとめ:溶融亜鉛めっき高力ボルトについて正しく知ろう
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合は、適切な技術的配慮のもとで使用可能であり、メンテナンスフリー構造を実現する有効な手段です。
ただし、通常の高力ボルト接合とは異なる技術基準と管理体制が必要となります。
本記事で解説してきたポイントを押さえることが基本ですが、使用時は取扱説明書や技術資料を読み込み、理解を深めた上で施工を行いましょう。