豆知識
2025/08/29
亜鉛めっきの世界|電気と溶融、亜鉛めっき鋼板の違いを解説
おすすめ記事
- RANKING
- 最近人気の記事
- SDS(安全データシート)とは?見方をわかりやすく解説
- 溶融亜鉛めっき上の塗装はできる?耐食性と美観を両立させたい方は必見!
- 溶融亜鉛めっきの白さびは悪者?原因と対策、新たな視点を解説
- 溶融亜鉛めっきのJIS規格の改正について
- 専用シンナー(うすめ液)以外はNG!理由や不具合の事例を解説
- 溶融亜鉛めっきと異種金属が接触したら腐食する?メカニズムを解説
- 無機ジンクと有機ジンクは何が違う?1液と2液の違いも解説
- ジンクリッチペイントとは?亜鉛含有率との関係や防錆メカニズムを解説
- 溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
- 溶融亜鉛めっきと塗装は何が違う?両者の特徴をわかりやすく比較
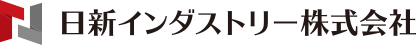
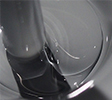





「亜鉛めっきの種類とそれぞれの違いがわからない...。」とお困りではありませんか?
亜鉛めっきは大きく分けて、電気めっき、溶融亜鉛めっき、亜鉛めっき鋼板の3種類があります。
本記事では亜鉛めっきの3種類を取り上げて、それぞれの特徴や選ばれる場面をわかりやすく解説していますので、亜鉛めっきについて深く知りたい方は必見です。
亜鉛めっきの基本原理
亜鉛めっきは、鉄鋼材料の表面に亜鉛の薄い層を形成することで、サビの発生を防ぐ表面処理技術です。以下2つの作用がサビから鉄を守ります。
亜鉛は鉄よりも酸化しやすい性質を持っているため、鉄よりも先に酸化することで鉄を保護します。
これを「犠牲防食」と呼び、亜鉛めっきの最も重要な機能です。
上の金属のイオン化傾向の画像で見ると、鉄(Fe)より亜鉛(Zn)はイオン化傾向が大きく、酸化しやすいことがわかります。
また亜鉛が酸化してできる酸化亜鉛は緻密な「保護被膜」を形成し、さらなる腐食の進行を抑制する効果もあります。
亜鉛めっきの3種類(電気、溶融、亜鉛めっき鋼板)早見表
亜鉛めっきの種類
特徴
耐食性・寿命
外観・仕上がり
電気めっき
電解液中で電流を用いて亜鉛を被膜する方法で薄膜で明るく均一な仕上がり
被膜は非常に薄いため耐久性は低く、寿命は短め
明るく光沢のある仕上がり。均一な色と見た目が求められる用途には適している
溶融亜鉛めっき
鋼材を溶融亜鉛槽に浸して亜鉛皮膜を形成
厚い被膜により耐食性と耐久性が極めて高い。50年以上使用されるケースもある。
一般的に銀白色の光沢があるが、時間の経過とともに灰色に変化する
亜鉛めっき鋼板
鋼板を連続処理ラインで電気めっきする方法。薄膜だが均一で加工性良好
膜厚は薄いため耐久性は中程度。溶融亜鉛めっきより耐久性は劣る
滑らかで光沢も良い
電気めっきの特徴
電気めっきは、電解液中で電気分解を利用して亜鉛を析出させる方法です。
上のイラストのとおり、処理対象となる鋼材を陰極とし、亜鉛を陽極として電解液中に配置し、直流電流を流すことで亜鉛イオンが鋼材表面に析出します。
電気めっきの製造工程は以下のとおりです。
電気めっきは被膜が均一で滑らかに仕上がり、光沢を持たせることも可能な為、外観品質が求められる製品に適しています。
しかし、他のめっきと比較すると被膜が薄いため、耐食性や耐久性では劣るのが特徴です。
溶融亜鉛めっきの特徴
溶融亜鉛めっきは、約420℃以上に溶融した亜鉛槽に鋼材を浸漬する方法です。
高温の亜鉛が鋼材表面と合金化することで、非常に強固な密着性を持つめっき層が形成されます。
溶融亜鉛めっきの製造工程は以下のとおりです。
溶融亜鉛めっきは50~150㎛程度の厚いめっき層が得られます。
長期間の防錆効果が発揮されるため、屋外の構造物に数多く適用されているのが特徴です。
鋼材との界面で合金層が形成されるため、めっきの剥離が起こりにくく、日々のメンテナンスが難しい場所で真価を発揮します。
亜鉛めっき鋼板の特徴
亜鉛めっき鋼板は、薄い鋼板に亜鉛めっきを施した製品で、現代の製造業において極めて重要な素材です。
主に「電気亜鉛めっき鋼板(EG)」と「溶融亜鉛めっき鋼板(GI)」、そして「合金化溶融亜鉛めっき鋼板(GA)」に分類されます。
亜鉛めっき鋼板の製造工程は以下のとおりです。
※合金化溶融亜鉛めっき鋼板(GA)では、めっき後に約500℃で加熱して鉄と亜鉛を合金化させる
亜鉛めっき鋼板は連続でめっき処理できるのが最大の特徴です。
電気めっきは薄く均一な皮膜で美観に優れ、塗装や精密加工に適しています。
一方、溶融めっき鋼板は厚い皮膜で防錆効果が高く、屋外や過酷環境で長期使用が可能です。
いずれも成形や溶接が可能で幅広い用途で使用されています。
3種類の亜鉛めっきがそれぞれ選ばれる場面
亜鉛めっきの種類
選ばれる場面
身近な使用例
電気めっき
・精密な寸法精度が求められる部品
・複雑な形状の小物部品
・美しい外観が重要な製品
・ねじ類など、厚いめっきが機能に影響する部品
・自動車のボルト
・洗濯機の内部部品
・スマートフォンの金属部品
・工具
溶融亜鉛めっき
・長期間の耐久性が最重要な構造物
・大型で厚い鋼材
・メンテナンスが困難な設置場所の構造物
・極めて厳しい腐食環境下での使用
・高速道路のガードレール
・信号機の支柱
・公園のフェンス
亜鉛めっき鋼板
・大量生産される薄板製品
・プレス成形や溶接加工が必要な製品
・軽量化と防錆性の両立が求められる製品
・塗装を前提とした製品
・自動車のボディパネル
・エアコンの室外機
・電子レンジの外装
上の表は3種類の亜鉛めっきがそれぞれどのような場面で活躍しているかをまとめたものです。
それぞれの特性を活かして使い分けられていることがわかります。
費用対効果を最大化するためにも、それぞれの工法の特性を理解することが大切です。
環境への配慮と技術革新
画像:ガルバリウム鋼板のイメージ
近年、すべての亜鉛めっき技術において環境への配慮が重視されています。
電気めっきでは、従来のクロメート処理に代わる環境負荷の少ない後処理技術の開発が進んでいますし、溶融亜鉛めっきでは、亜鉛の回収・再利用技術の向上により、資源の有効活用が進行中です。
亜鉛めっき鋼板の分野では、より薄い膜厚でも高い耐食性を発揮する技術やリサイクル性を向上させる技術の開発が活発に行われており、自動車業界では軽量化のニーズに応えるため、高強度鋼板への亜鉛めっき技術も進化しています。
特に注目すべきなのが、ガルバリウム鋼板です。
亜鉛にアルミニウムとシリコンを加えた合金めっき鋼板で、従来の亜鉛めっき鋼板より優れた耐食性と耐熱性を実現しています。
住宅の屋根材や外壁材として広く普及し、スタイリッシュな外観と高い機能性を兼ね備えた素材です。
現代のインテリアデザインにおいても亜鉛めっき製品が新たな役割を果たしています。
天井を取り外したスケルトン天井のカフェやレストランでは、従来は隠されていた空調ダクトや配管があえて露出され、工業的で無骨なデザインとして人気です。
これらの設備には亜鉛めっき鋼板が使用されており、機能性を保ちながら現代的でオシャレな空間作りに貢献しています。
まとめ:亜鉛めっきの補修なら日新インダストリーまでお問い合わせを
亜鉛めっきは製品の防錆効果を高めて長寿命化を実現するために必須の表面処理です。
しかし、製品によっては経年劣化によって防錆効果が薄れていくことがあるため、定期的な補修が欠かせません。
もし亜鉛めっきの補修でお困りであれば日新インダストリーまでお問い合わせください。
お客様のお困りごとをヒアリングさせていただき、亜鉛めっきの補修で使用できる最適なジンク塗料をご提案いたします。