使用方法
2021/07/12
塗料を保管する5つのポイント
おすすめ記事
- RANKING
- 最近人気の記事
- HDZT77とは?HDZ55からの変更点と溶融亜鉛めっきJIS改正を解説
- SDS(安全データシート)とは?見方をわかりやすく解説
- 溶融亜鉛めっきの白さびは悪者?原因と対策、新たな視点を解説
- 溶融亜鉛めっき上の塗装はできる?耐食性と美観を両立させたい方は必見!
- 専用シンナー(うすめ液)以外はNG!理由や不具合の事例を解説
- 溶融亜鉛めっきと異種金属が接触したら腐食する?ガルバニック腐食のメカニズムを解説
- 無機ジンクと有機ジンクは何が違う?1液と2液の違いも解説
- ジンクリッチペイントとは?亜鉛含有率との関係や防錆メカニズムを解説
- 溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
- 溶融亜鉛めっきと塗装は何が違う?両者の特徴をわかりやすく比較
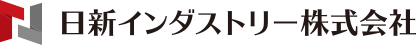
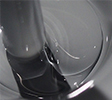





今回のコラムでは、意外と見落としがちな塗料の保管方法についてのお話です。
「塗料の保管なんて、蓋して置いとけばいいんじゃない?」
と思う方もいらっしゃるかと思いますが、
保管方法を間違えると、使用するときに塗料に異常が発生して使用できなくなっているなんてことも。
場合によっては、塗料缶・スプレーの破裂等の思わぬ危険に遭遇してしまう可能性もあります。
そのような事態が起こる前に、今回は弊社製品を例に塗料を保管する5つのポイントを挙げていきます。
【塗料を保管する5つのポイント】
1、高温・多湿や直射日光を避けて保管する
2,水性塗料は0℃以下の場所を避けて保管する
3,容器は立てて保管する
4,塗料缶はフタをして保管する
5,スプレーは使用後に空吹きをする
1,高温・多湿や直射日光を避けて保管する
容器のさびやすい湿った場所や、40℃以上になる場所で保管すると、
製品の外観だけでなく、中身の塗料に異常をきたす可能性が高くなります。
粘度上昇・ゲル化(中身の塗料がゼリー状に変化)・ぶつ・硬沈降・色わかれ等が発生し、
現象によってはシンナーを入れても元に戻ることはなく、使用できなくなります。
塗料異常については、また別の機会にコラムを掲載しますね。
2,水性塗料は0℃以下の場所を避けて保管する
水性塗料は水を成分として含有しているため、氷点下になるとその成分は凍ります。
そうなると本来の塗料成分ではなくなり、十分な性能を発揮できません。
0℃以下が長時間継続するような場所では保管しないでください。
3,容器は立てて保管する
塗料缶のジンクリッチペイントは、ガス抜きキャップのため、
横に倒すとキャップから塗料が漏れます。必ず立てて保管・使用してください。
4,塗料缶はフタをして保管する
保管中はもちろんですが、使用中も可能な限りフタをしてください。
一斗缶は天板から開けているはずですので、
長時間塗料を保管するようであれば一斗缶用のフタの使用をお勧めします。
フタを開けたまま放置してしまうと、溶剤が揮発し、塗料の成分バランスが崩れ、
塗料本来の性能を発揮出来ない可能性があります。
5,スプレーは使用後に空吹きをする
エアゾールスプレーを使用後、そのままの状態で保管をすると缶内部のチューブに亜鉛末等の塗料が固化し、目詰まりの原因になります。
使用後の保管や一時的に使用を止めるごとに、エアゾール缶を逆さまにして3秒ほど空吹きをしてください。
以上が5つのポイントとなります。
見てみれば、既に知っていることだったり、
意外に難しいことではないんだなと分かって頂けたと思います。
蓋を開けっ放しにしていたら塗料が使えなくなっているなんてことがないように、
この5つのポイントを押さえて塗料を安心・安全にお使いください。
>>>製品一覧はこちらから