豆知識
2025/08/29
溶融亜鉛めっきとは?防錆のメカニズムや他のめっきとの違いを解説
おすすめ記事
- RANKING
- 最近人気の記事
- SDS(安全データシート)とは?見方をわかりやすく解説
- 溶融亜鉛めっき上の塗装はできる?耐食性と美観を両立させたい方は必見!
- 溶融亜鉛めっきの白さびは悪者?原因と対策、新たな視点を解説
- 溶融亜鉛めっきのJIS規格の改正について
- 専用シンナー(うすめ液)以外はNG!理由や不具合の事例を解説
- 溶融亜鉛めっきと異種金属が接触したら腐食する?メカニズムを解説
- 無機ジンクと有機ジンクは何が違う?1液と2液の違いも解説
- ジンクリッチペイントとは?亜鉛含有率との関係や防錆メカニズムを解説
- 溶融亜鉛めっきの不めっき処理とは?失敗例や最新の不めっき剤を紹介
- 溶融亜鉛めっきと塗装は何が違う?両者の特徴をわかりやすく比較
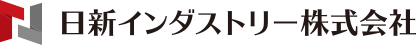
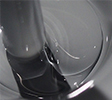





「溶融亜鉛めっきのメカニズムや他のめっきとの違いを知りたい!」とお考えではありませんか?
溶融亜鉛めっきは高い防錆性能で素材をサビから守るために有効な表面処理方法です。
メリットも多いですが、デメリットもあるため、防錆を検討している製品に適しているか見極める必要があります。
本記事では溶融亜鉛めっきについて防錆のメカニズムから他のめっきとの違いまで網羅的に解説しています。
溶融亜鉛めっきについて深く知りたい方は必見です。
溶融亜鉛めっきとは?
溶融亜鉛めっきとは、金属の表面に亜鉛の皮膜を形成することで、錆を防ぐための表面処理方法です。
特に鉄鋼製品に広く用いられており、防錆性能の高さから、さまざまな分野で重宝されています。
ドブ漬けとも呼ばれるほどシンプルで信頼性の高い防錆処理として有名です。
溶融亜鉛めっきの方法
画像:めっき槽から引き上げるイメージ
溶融亜鉛めっきの一般的な方法は、溶融した亜鉛の浴槽に鉄製品を浸漬させることです。
上記が一般的な溶融亜鉛めっきの処理方法です。
複雑な形状の製品でも、均一にめっき被膜を形成できるのが大きなメリットとなります。
溶融亜鉛めっきの防錆効果を支える2つの作用
溶融亜鉛めっきの高い防錆効果を支えているのは以下2つの作用です。
それぞれの作用を詳しく確認していきましょう。
亜鉛が先に溶け出す「犠牲防食作用」
溶融亜鉛めっきが高い防錆効果を発揮する最大の理由が犠牲防食作用です。
鉄と亜鉛が接している状態で、両者が電気を通す環境に置かれると、イオン化傾向が大きい亜鉛が鉄よりも先に腐食するという性質を利用しています。
上の図のとおり、鉄の表面に傷がついて鉄が露出しても、周囲の亜鉛が代わりに溶け出して鉄を守るのが特徴です。
まるで亜鉛が自らを犠牲にして鉄を守っているかのように見えます。
犠牲防食作用により、めっき皮膜の一部に傷が入っても、広範囲にわたってサビの進行を食い止められます。
亜鉛の被膜が錆から守る「保護被膜作用」
鉄の表面を亜鉛のめっき被膜で完全に覆うことで、水や酸素が鉄に直接触れるのを防ぎ、錆の発生を物理的に遮断するという作用です。
保護被膜は水に溶けにくいため、外部からの腐食因子を強力にブロックし、長期間にわたって鉄を保護し続けます。
溶融亜鉛めっきのメリット・デメリット
メリット
デメリット
・高い防錆性能
・強固な被膜
・あらゆる形状に対応できる
・メンテナンス頻度が低くて済む
・処理コストが高い
・光沢が不均一になる可能性がある
・亜鉛浴に入るサイズしか処理できない
・処理時に亜鉛の蒸気が発生する
上の表は溶融亜鉛めっきのメリットとデメリットをまとめたものです。
最大のメリットは強力な防錆性能であり、高い耐久性から何十年もメンテナンスをせずに使用されている製品もあります。
ドブ漬けする処理方法ですので、複雑な形状でも難なく対応できるのもメリットです。
一方で亜鉛を大量に溶かすための電力が必要であり、処理コストは電気めっきなどと比較して高額になります。
光沢が不均一になる場合もありますが、こちらは溶融亜鉛めっき独特のスパングル柄として意匠性が高いとされることもあり、一概にデメリットとは言えません。
溶融亜鉛めっきが選ばれる場面
分野
活躍する場面
インフラ関連
道路のガードレール、電柱、通信塔、鉄道関連施設
建築・建設
建築物の鉄骨、階段、手すり、配管
農業・水産業
ビニールハウスの骨組み、畜舎の構造物、漁網関連部品
産業・工業
工場の設備、配管、輸送機器の部品
上の表は溶融亜鉛めっきが活躍する場面を分野別にまとめたものです。
溶融亜鉛めっきは高い防錆性能を持つことから、腐食するリスクが高い屋外での構造物や工場での設備関連で幅広く使用されています。
インフラ関連では長期的な安全性とメンテナンス頻度の低さが重要視される箇所で不可欠な存在です。
建築・建設分野では構造物の寿命を延ばすのに貢献しています。
農業・水産業においても、湿気や腐食性物質に触れる機会が多い環境で重宝されており、産業・工業分野では、工場の設備や配管、輸送機器の部品など、過酷な条件下で稼働する製品の防錆対策として広く採用されて、設備全体の信頼性向上には欠かせません。
その他のめっきの特徴
溶融亜鉛めっき以外の、亜鉛をめっきする方法は主に以下の2種類です。
2種類のめっきの特徴を知って、溶融亜鉛めっきとの違いを確認しましょう。
電気めっき
電気めっきは、電気の力を利用して金属の表面に亜鉛を析出させる方法です。
溶融亜鉛めっきと比較すると膜厚が薄く、表面が滑らかで光沢があるため、美観を重視する製品に適していますが、膜厚が薄いので防錆性能は劣ります。
家具や家電製品、ボルトやナットなどで活用されるめっき方法です。
亜鉛めっき鋼板
亜鉛めっき鋼板は、鉄板を製造する段階で連続的に溶融亜鉛の浴槽を通過させて作られる製品です。
溶融亜鉛めっき鋼板は「GI」と呼ばれます。
亜鉛槽で単発的に処理する溶融亜鉛めっきとは製造工程が異なり、板状製品を効率的に製造可能です。
加工性が高く、曲げやプレスなどの加工に適した工法です。連続で処理する分、膜厚が薄くなるため、溶融亜鉛めっきよりも耐久性は劣ります。
自動車のボディ、家電製品の外板、屋根材、外壁材などが活用例です。
溶融亜鉛めっきの補修の必要性
溶融亜鉛めっきは耐久性が高いですが、切断や溶接、ボルト接合などを行うと亜鉛皮膜が失われ、鉄が露出してしまいます。
このまま放置するとサビが発生して、めっき被膜の下にまでサビが広がる可能性があります。特に、以下の箇所は重点的な補修が必要です。
補修が必要な箇所
補修が必要な理由
切断面、溶接部
亜鉛が除去されて、防錆効果が無いため
ボルト接合部
ボルトを締め付ける際にメッキ被膜がはがれるため
傷が発生した箇所
重いものがぶつかったり擦れたりするとメッキ被膜が剥離するため
これらの箇所を適切に補修することで、溶融亜鉛めっき本来の防錆性能を維持し、製品の寿命を延ばせます。
まとめ:溶融亜鉛めっきの補修にはジンク塗料がおすすめ
溶融亜鉛めっきの補修には、ジンク塗料がおすすめです。
ジンク塗料は、亜鉛の粉末を含んだ塗料で、補修箇所に塗装することで露出した鉄をサビから守れます。
溶融亜鉛めっきほど強力ではありませんが、犠牲防食作用と保護被膜作用があるため、他の塗料よりも防錆力が高いのが特徴です。
日新インダストリーが溶融亜鉛めっきの補修用に開発したジンク塗料は、下地のめっき皮膜との密着性も高く、補修後も長期間にわたって効果を発揮します。
スプレータイプもご用意しており、手軽に補修できるため、現場での作業にも最適です。
溶融亜鉛めっきの補修にお困りの方は、お気軽に日新インダストリーまでお問い合わせください。最適なジンク塗料をご提案します。